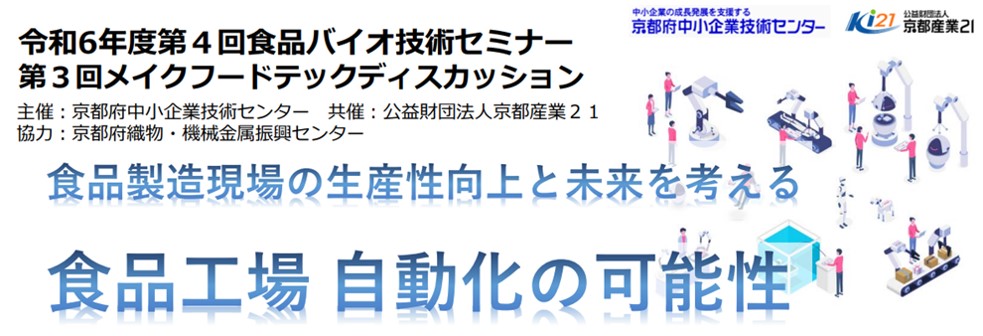
【開催概要】
令和7年2月21日(金)に令和6年度第4回食品バイオ技術セミナーを開催いたしました。セミナーには食品製造業、自動化設備製造業、支援機関の方を中心に、会場約30名、オンライン約40名の方々にご参加いただきました。
食品工場自動化の可能性を考えることをテーマとしたセミナーで、立命館大学の平井慎一教授から食品工場現場でのロボット技術活用事例、同大学の山崎文徳教授から技術によって経営を動かす事例に関わるお話を伺いました。その後のパネルディスカッションでは、お二人の先生に加えて、OEMでレトルト食品を製造する日本調味食品株式会社の奥村正男社長と自動化設備を設計製造する株式会社J・P・Fエンジニアリングの田中丈治社長にもご登壇いただき、食品工場の自動化に関わる課題や解決策、事例などについて受講者の皆さんにも意見をいただきながら議論を交わしました。
その後、会場での名刺交換会でも個別に挨拶や情報・意見交換が活発に行われて、講師と受講者の間では後日の工場見学や具体的なディスカッションを行う話に発展している様子も見受けられました。
【各パート振り返り】
開催事務局として当日の司会進行・ファシリテーターを担当とした京都府中小企業技術センターの植村の視点と解釈で各パートを振り返ります。
講演① 「食品製造現場でのロボット技術の活用について」
立命館大学ロボティクス研究センターの平井慎一教授からソフトロボティクス研究について多くの事例とともに解説していただきました。工場での自動化ロボットと言うとロボットアームが思い浮かべられがちです。大手ロボットメーカーは汎用性が高く、量産しやすいアームの部分を提供してくれますが、食品工場ではとくにハンドの部分の最適化が重要になってきます。ハンドは把持したいものに合わせて設計・製造する必要があり、オーダーメイド対応が主流となりますので大手は参入しにくい背景があります。平井教授のチームでは食品を壊さずに、こぼさずに、素早く移動させるための柔らかい素材を用いたハンドの設計・試作の研究開発を実際の企業現場の課題に向き合いながら取り組んでおられます。
形状や機構の異なる様々なハンドでの試行錯誤を積み重ねてきたことで、課題に合わせて、どのような選択肢が有効かを選ぶノウハウも高まってきているということでした。
とくに気になった先進事例としては、国の補助事業で広島の企業が取り組まれた牡蠣フライ製造ラインでの搬送自動化に立命館大学が関わっており、動画も交えてハンドの設計や3Dプリンタを用いたハンドの製造について教えていただきました。これに大学が関わったキッカケも先生の講演を聴いた企業から声掛けがあり、支援につながったのだということです。
平井教授には企業からの相談はウェルカムという姿勢をセミナー中にも見せていただき、名刺交換会では参加企業様との次の動きにつながりそうな様子も見られました。もし今後、食品工場での自動化による生産性向上の新しい好事例が生まれたとき、実はこのセミナーがキッカケだったんだという話を聴けることを期待して、引き続き、京都産業21ともタッグを組んで技術、経営両面からの企業支援を続けてまいりたいと感じました。
講演② 「技術と経済的価値創造をつなぐ技術経営について」

立命館大学経営学部で技術経営論についての研究、教育をされている山崎文徳教授から食品工場の自動化を検討するときにも重要な技術経営論的視点を解説いただき、技術開発・導入により製品や生産の姿を変えてきた企業事例を紹介いただきました。
山崎教授の専門は航空機産業分野での技術経営論ですが、学生指導のゼミ活動では食品工場や半導体工場などにもフィールドを広げてらっしゃいます。
まずは、様々な産業分野で共通する考え方として、製品の技術競争力と生産の技術競争力の2つを高めることの重要性を教えていただきました。
製品の技術競争力という視点では、多様なニーズに応えるためには多層的で多様な製品群を用意することが重要である一方で、すべてが多品種少量や特注仕様ではスケールメリットが得られにくいため、いかに中核部分を標準化した上で対応しやすいオプションで多様なニーズに応える製品技術を確立することがひとつの戦略になり得るということです。
生産の技術競争力という視点では、技術の開発や導入がどのように経営的メリットを生み出すかを4つの効果に分類し、「労働生産性の向上」、「原材料や機械装置の節約」、「資本の回転率の向上」、「変種変量生産の実現」といった効果がどう経済的価値に変換されるかを検証する考え方を教えていただきました。
食品産業での事例として、茶葉から缶緑茶飲料、ペットボトル緑茶飲料という製品の変化をたどる中で、どのような技術導入があったのか、技術導入により製品の形態や品質、生産性がどうなり、競争力を生み出したのかについて紹介、解説いただきました。また、製造業(食品加工メーカー)と流通業(コンビニエンスストア)との関係性が技術開発や価格決定に影響するおにぎりの事例も紹介いただきました。
パネルディスカッション 「食品工場 自動化の可能性」

パネルディスカッションには、奥村社長と田中社長にもご登壇いただき、食品メーカーと設備メーカーの立場から議論を広げ、深めていただきました。
また、Slidoというツールを使って、会場・オンライン双方の受講者の意見を収集しながら議論を進めました。
田中社長からは1回の簡単なティーチングで24時間働くロボットの開発と中小企業向けのコスト感を紹介いただき、奥村社長からは食品メーカーでの人材確保が難しくなってきており、このまま問題を放置していては食品メーカーには黒字廃業せざるをえないメーカーも出てくるのではないかという危機感、現場の従業員からも機械化や自動化は望まれているという現状をお話いただきました。
とくに気になった議論は、食品メーカーと設備メーカーの付き合い方の文化は欧米と日本で異なる部分があって、欧米は設備に合わせて製造する文化、日本は製造現場にあわせて設備を合わせる文化という傾向があるものの、製造現場と設備、流通がもっと対等に知恵を寄せ合いながら最適解を求めていくということが必要なのではないかという議論。また、自動化した場合の段取り替えのための交換や洗浄の工数削減が現場視点では重要なポイントであり、それに対して、例えば、ロボットハンドに人間と同じように使い捨て手袋をつける方法や人の手指消毒なみの作業時間で段取り替えできる工夫があり得るのではないかという議論もありました。
京都府産業支援センターでは技術支援の中小企業技術センター、経営支援の京都産業21、知財支援の発明協会の三位一体での企業支援を行っています。今回のセミナーが技術と経営の両面から課題に向き合い、ネットワークを拡げる場の提供になっていれば幸いです。
本記事のPDFファイルを以下のリンクからダウンロードいただけます。保存用、印刷用などにご利用ください。